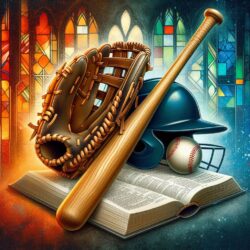【扉を開けるカギ】の第4話は初めて世界大会という大舞台に挑む代表監督の話。
彼は地域の代表チームの監督を初めて任されることになった。
厳しい国内予選を勝ち抜き見事優勝を果たす。
続くアジア大会でも優勝し、世界大会の切符を掴んだのだった!
彼は世界大会に挑む前にどうしてもチョンミョンソク牧師からコーチングを受けたかった。
世界大会に出発前、チョンミョンソク牧師のもとを訪れ、コーチをしてくださいと依頼した。
世界大会という大舞台に挑む代表監督に向けてのチョンミョンソク牧師のコーチングはどのようなものだっただろうか?
チョンミョンソク牧師のコーチングは以下の3つだった。
“정신일도”
“精神一統”
“하늘의 운에 타야 된다”
“天の運に乗らなければならない”
“감각이다”
“感覚だ”
もうすでに天の運に乗って世界大会進出を決めたことは誰も否めないだろう。
著者は世界大会の様子をすべて中継で見守った。
結果は惜しくも3位だった…
いや、惜しいという言葉は全く必要ない。
初めて代表チームの監督に選出され、国内予選・アジア大会を勝ち抜き、世界の舞台で3位になったのだから何が惜しいだろうか!
ハレルヤ!
野球選手のみならず、全てのスポーツ選手は、重要な試合・大会には、このチョンミョンソク牧師のコーチングを必ず思い出してほしいと思う。