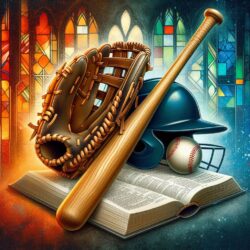先日、一歩間違えば命を落としかねない事件が起こった。
練習前に選手が悪ふざけをして、凍った川の上を歩いていた…
普段は比較的流れの速い川だが、日中も氷点下の気温が続いたため凍った。
とは言え、人が乗って耐えられるほどの分厚さではなかっただろう…
その選手は氷が割れて落ちた…
現場を目撃してはいないが、後で本人に話を聞いてみると、氷が割れて膝上まで水に浸かったとのこと…
幸いにも流されずに済んだが、震えながら家に帰った…
面白半分で、好奇心で何かをすることがあると思う。
しかし、その末路を全く考えずに行なうことは非常に危険だ…
幼い選手たちはそのような危険予知能力が乏しい。
だから常日頃から教育を繰り返さなければならない。
自分の命を自分で守ることができるようにしてあげなければならない。
今回の一件、大事に至らなくて本当に良かったのだが、良かったでは終わらせてはいけない問題。
練習前の選手の動きまで統制することは難しいし、あまり縛ってはいけないが、目の届かないところで問題が起こらないように教育しなければならないと気を引き締めた。
選手たちを育てて素敵な野球選手に作る以前に選手の命を守る指導者にならないといけないと、この一件を深く心に刻みたい…